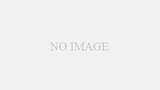このブログ、去年の3月10日頃より始めたので、そろそろ一周年です。
ほぼ毎日、勤勉に書きましたから、もう366件投稿してます。一日に二回書いたことがあるようです。
夏の終わりに第一期を終えて、第二期にはいりました。一年経ったところで、第三期に入ろうかと思います。進歩がなくても、なんらかの変化を示したいのです。
最初は定年制度への怒りのようなものがあって、それを基盤に書き出したような面もありますが、基本的にはわたくしの気晴らし、まさに仕事のあいまの休憩時間に泡のようにわいてくる考えを書きつづったものです。
科学についての事件を書くと、より多く読まれるようです。捏造論文事件のことを書くと、このブログへの訪問者が増えます。しかし、読む人を増やすために書いてるのでもないし、捏造事件なぞは本当は書きたくありません。知り合いの阪大のみなさんの顔を思い浮かべるととほんとに書きにくいことです。
しかし、もしもわたくしの所属する京大の生命科学研究科で似たような捏造事件が発覚すれば、わたくしの筆致は極めて厳しいものになることは間違いありません。わたくしはこのような問題で身内に甘くすることはまったくありませんので、お許しを。ただ、京大の場合、わたくしがそういうことをすれば、この一年ずつ更新される研究員の職を賭けるようなことになるかもしれません。つい、数日前に研究科長さんからわたくしのこの研究員の職が教授会でまた一年延長することを許可する議決が行われたそうです。もう一年、首がつながったわけです。たいへん、ありがたいことです。教授のみなさんに深く感謝せねばなりません。
そういう状態にわたくしはおりますので、こういう問題に逆に気楽に論じることが出来る面もあるのは事実です。
しかし、この深刻な問題をとりあげて論じる人が現役研究者でたいへん少ない、それで希少価値があると、いままでに多くの人に言われました。そういう人達にも発言してほしいのですが、ともあれ、この希少価値ということばにわたくしはたいへん弱いのです。わたくしの研究態度は、すくなくともはじめる時は希少価値を求めて始めてるのです。何年かすると似たようなことをする人が多いのに気がつくのが昨今の傾向です。誰もやらないことを5年くらい続けるのが難しいものです。
前置きが長くなりましたが、研究の成果というものは、結局対話を続けることによって発表されるものです。
まず自分との対話。そろそろ発表してもいいのではないか。
ごく周辺との対話。ラボのメンバーや近い研究者などに話すと、まわりもそろそろ公表すべきではないかといってくれる。
過去の研究との対話。論文などをまとめ出す過程で、過去の研究を精査してみると、十分に新規性がある。しかし、似たような考えや成果がもう既に発表されていたり、もしくは今回の結果と一致しないこともあったりするといろいろの対話がひつようになります。
学会などでの対話。学会で発表しての、受け止められかたが、手応えがあり、元気づけられる。しかし、全くなかったり、予想外だったりすれば、また対話が必要かもしれません。
論文を書いてからの、レフェリー、エディターとの対話。ここを通過しなければ、研究成果は公表できないので、通常はいちばん念入りな対話が行われるのです。
論文公表後の対話。不特定な人達が読んでくれて、コメントをいわれたり、なんらかの反響があり、そこでまた対話があるはずです。そして、みずからにフィードバックした対話があるはずです。つまり公表したことの総括的な対話です。
研究の成果を発表する過程で、自分が生みだしたデータや新しい考えが、他のいろいろな人達との対話を通じて、パブリック、公共のものになっていくのです。
研究のほとんどすべては、この公共の知識を生みだすための努力をしているわけです。
もしもわたくしが発表したことが誤っているとか、いわれたらその人とはぜひ徹底的に対話したいものです。またもしも捏造データがあるなどといわれたら、徹底的に調べて説明と対話をしなければならないでしょう。
研究成果はひとたび公表すれば、公共的な財産ですから、自分の占有的な所有権などあるはずもありません。しかし、その知見をもたらした人間の責任として、誤りがふくまれていれば、その点を明確にする責務があるわけです。
対話によって、真理に近づいていく、これが21世紀における科学研究の世界での常識です。
昨日の朝日新聞夕刊を見ると、阪大での捏造論文事件で当該捏造をしたといわれている、学生がインタビューに応じている記事がでています。
学生は捏造を改めて否定し、画像を操作する能力が自分にない、といってるとのことです。学生は画像を改ざんしたのは、指導役の研究員だとのことで、その理由もデータが汚かったからというものです。また遺伝子改変マウスはあったのだが、動物飼育責任者の管理ミスにより、置きかわったとのことです。
また、実験に再現性はあり、論文は取り下げるべきではなかったと、主張しているとのことです。
関係の研究者および本事件の調査委員会報告がいってることと、まったく異なることをいってるわけです。
このような論文の筆頭著者本人の主張をマスメディアが取り上げて記事にしたからには、対応する義務が、関係の研究者、とくに調査委員会は説明義務があると思われます。
国民の税金を使って行われた研究である以上、対応する責任が大学当局、関係研究者にはあるでしょう。
また大学当局は学生が、調査に協力したのに(大学に)騙された、とか学生を更生するのが目的なはずの医学倫理学教育プログラムはただの雑談であるといいってることなどは、大学の処分についての完全否定であり、更生プログラムに対する重大な挑戦と認識する必要があるのではないでしょうか。
このような、メディアの報道に対してもしも関係者が知らぬ存ぜぬを通すつもりなら、またパブリックと対話する機会を逸するのならば大変に残念でなりません。
またもちろん当該学生と真の意味での対話を完全に怠っているのではないでしょうか。