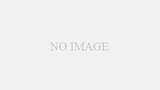今の時代、少年少女たちは研究者になろうとか思うような機会はどれくらいあるのでしょうか。わたくしは、かつて書いたことがあるのですが、漠然とそんな夢というか、なってみたいと思ったのは、小学校の高学年の頃でしたが、家族の誰かが学者でもないし、雲をつかむような話しでした。これも、前に書きましたが、大賀ハスという千年前のハスの種が花を作ったというニュースを強く印象に刻みました。いまの時代だとどんなことを契機に学問でもやってみたいと思うのでしょうか、はっきりいってまったくわかりません。それじゃ困るのだけれども、手がかりになるいまふうの知識がないのです。
最近ときたま話題になっている京都の堀川高校、京大現役での合格率が全国最高とか、彗星のようにあらわれた公立の有名高校らしいのですが、かつてラボに学生時代にいたF君が生物の教師をしています。
彼から聞くとやはり高校生くらいでは、学者というか、研究者になりたいとおもう生徒達はかなりいるようです。それは、とても嬉しいしらせなのですが、そのあと彼等がどうなっていくのか。楽観主義でいってほしいなと願うばかりです。
科学研究というのは、楽観的な生きるプランを持ってないと、なかなかやってけるものではありません。というか、夢想家つまり楽観的人生観をもってればかなり楽しくやってけるはずのものです。
アカデミアというか、学術研究の雰囲気というのはそれ自体、とてつもなく楽しいものです。ルールがわかって、自分がどう働けば、どうなるのかわかりだしてくると、こんな素晴らしい世界があったのか、とただただ感心したものです。
データが好きで、考えることが好きで、論文を読むのが楽しければ、もう職業的実験研究者になるための条件はほとんど整っています。
ただ、楽観主義を捨てて、成功シンドロームのほうに向かうと、研究も学術もなにひとつ楽しいものはありません。成功は結果であって、あれば嬉しいし、自信もつくでしょうが、成功、不成功で二色に分けたら、いっぺんに緊張とストレスの世界にいってしまいます。
きょうの会議のあと、こんなことを考えました。結局学問が継承を第一にする以上、学問に憧れるような少年少女が確実にいて、かれらが順調に学問というかアカデミアの世界にやってこれて、予想通り楽しいところと感じて、伸び伸びと学問、研究に励む、こういう世界を作らなければ、何も始まらないのだなとおもいます。そのうえでの、学術体制なのでしょう。
きょうの会議は4時間以上もやりましたが、Tさんの闊達にして明解な会議の運営もあり、わたくしはかなり楽しめました。手続き論に終止しがちな他の委員会とは大違いでした。