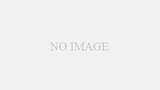けさ文科省の副大・政務官臣宛にメールを送りました。
このブログで昨日に書いたような意見をかきました。
昨日のあさ沖縄のラボにいく前に急いで書いて、怒りのあまり、注意深くかいてないな、と自分でも気がついて出かけたのですが、かえって非常に多くのご意見をあつめたようで、その点では良かったかな、と思った次第です。ただ、人やなにかを批判すれば自分が批判されるという当たり前のことに改めて気がつきました。
さてきょうは京都のラボに戻って、いま午後6時です。忙しい日でした。まだ、これからやるこがあるるので、書ける時間がちょっとしかありません。
それで、先端研究のことだけだけでもすこしつけ加えて起きたいのです。
わたくしの考えている先端研究の理想形とは、個人の創意から発想した研究です。どんなテーマでもいいので、なおかつ本人のつもりとしては、フロンティアでの成果をあげようとするものです。つまり、ボトムアップ型申請となります。
研究室の人件費とかを考えると、科研費でいえば基盤Sとか特別推進のような比較的高額の研究費が当たれば数年間思い切り研究ができることになります。
このようなボトムアップの研究に対して国策的といわれるトップダウンの先端研究があります。つまり研究テーマが最初から決まっているのです。
わたくしはこれになんら反対するものではありませんが、しかしどのような理由と経緯でそのような国策といわれる研究プロジェクトが選ばれたのかをなるべく透明に分かるように説明して欲しいとおもうのです。また過度に「役に立つ」ことを強調することは決してよい研究を生みだすものではないとも思っています。山中さんのお仕事だって、初期には個人の創意と好きでやってたので、トップダウンに沿ってやったわけではないでしょう。
先端研究とそうでないものの区別などはじっさいのところほとんど意味がない、と思います。やっている研究者本人の心意気で決まることでしょう。
わたくしは先端研究という言葉は好きでないのですが、行政が使うのでしかたなく使う程度です。やる気がある人がやろうとすることなら、なんでも先端研究、フロンティア研究なのでしょうがしかし、他人がそう認めるかどうか、優れた先端研究といわれるのはなかなか大変かもしれません。
何年も経って、結果をみて先端の結果をだしたという評価がおろされるのでしょう。
国家が維持する研究の頂点となる成果はは結局は個人の創意から出るものです。
それは芸術だって同じことでしょう。
わたくしは伝統主義者なので、過去の人々の偉業を学んで未来に対するエネルギーを蓄えてきました。わたくしの人生そのものがそういう過去の人々の魂を受け継ぎたいという欲求から成りたっています。
日本人の場合、特に明治以降の辛酸をなめるような努力は本当に大変でした。
わたくしは、先人に対する心からの尊敬とかれらの魂を少しでも分かち合って、受け継ぎたいと思っているのです。いまでもそういうつもりでやっています。ですから、わたくしの考える先人のパンテオンがあるからこそ、まだまだ未来に対するエネルギー維持できるとおもうのです。