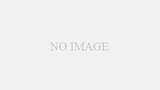わたくしは宗教には無頓着ですが、でも実際にはしばしば考えています。宗教的ではなくて好奇心いうか知的好奇心で宗教に関心があるのです。特に沖縄に来てから沖縄の宗教心の根っこみたいなものを理解したくおもっております。
わたくしは祈る心は持っているので宗教心はいちおうありますが、でも一方でたたりを怖れる気持ちは相当あるので自分の宗教心はまったく洗練されてないと自認してます。
それでつい先日購入した本を読んでいたら、日本の神社の中で一番数の多いのが八幡さん八幡神社なのだそうです。誰かの名前が付いているのが多いので、特に武将のが多い。これはもちろん武人を顕彰する意味合いもあるが案外たたりを怖れている面もあるらしい。天神さんは二番目に多いのだそうですがこれも菅原道真公のたたりを怖れたひとたちが建物を建てたのが始まりとか聞きます。
実在の人物を護る神社をつくるなど日本人の宗教心の柔軟さというか自由さを感じます。
この本では、だいたい神社というのは当初は建物は無かったし、なんにもないような大きな岩の前あたりで儀式祈祷などを行うのが本来の姿で、神道の心髄はなんにもないのだと、と書いてあります。
なんにもないというと妙に納得してしまいます。あまりあるくらいに内容のありすぎる仏教とは千年以上もうまっくいったのはそれが原因とか。これもうなづけます。
沖縄の宗教の原風景は本島南部のセイファーウタギだろうとおもうのですが、あれが本来の神社の原風景なら納得してしまいます。
こんごこの本が推薦する神社の原風景的なところも訪問したくなりました。
セイファーウタギは中世から近世にかけて盛んになったのですから新しいのですがでもスタイルは神社の原風景といわれると理屈抜きに納得したくなるのです。
沖縄では仏教の影響は非常に少なく見えます。ですから、沖縄と本土の岩石のあるところでの宗教的な齊場を色々おとずれると新しい発見があるような気もします。
ただわたくしは神道の神様は八百万の神様なのでたくさん、無数にあるので、それがキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の一神教とは根本的に異なると説明されてるところがあまり腑に落ちないのです。
それが定説なのかもしれませんが、わたくしは神道はユダヤ教やイスラム教とどこか似ていて、姿かたちが見えない神様とどうつきあうのか、という点で共通性があると。
イスラム教のモスクは巨大なところにいったのでわかりませんが、ユダヤ教のとても小さな教会シナゴーグなどは神社と雰囲気が似ているとおもいました。
見えない神様を気でかんじる神道は、なかなかいいものだと感じます。八幡神社のようにいろいろな過去の人物をおもいおこす場所もありますが、それも別に神様を思う上で邪魔になりませかし歴史を感じておもしろい。
いま京都で外国人に一番人気があるのが伏見大社とかききました。
外国人に親しまれる神社が増えることを願います。
神道にしたしみ岩石、巨岩信仰という人類のもっとも古い信仰心の元での共通性に気がつけば、日本の神道の普遍性に多くの人々が気がついてくれるはずで、そうなれば無数の日本中にある神社が世界の人々の関心の対象になるかもしれません。そのためにも外国人にもよくわかる伏見稲荷のような神社が増えるといいですね。